本社ヶ丸(ほんじゃがまる)
2009年10月31日(土)
♪ホンジャガジャガジャガ、ホンジャガジャガジャガ、ホンジャガジャガジャガジャガ!まる。
出発前から頭の中でこのフレーズがぐるぐるエンドレスで鳴っています。ちょっと変わった山名に惹かれ一度予定したものの体調不良で断念。でも今日は雲がなく絶好の登山日和。よーし、一丁登ったるかぁ!
恒例の7時発スーパーあずさで大月へ。そこで後続の各停に乗り換え2つ先の笹子駅へとやって来ました。
十数人は降りたでしょうか、みなさんそれぞれ目指す方向へと歩いていきます。我が隊も早速出発進行!の前に、隊員のトイレタイム。これが結構混んでて時間がかかりました。

駅を出たのが8時46分。まずは甲州街道を左に進み追分方向へ歩くこと30分。道の左側に笹子鉱泉と看板の出た建物を過ぎれば、ようやく「本社ヶ丸・清八峠」とある標識が現れます。
この標識のある所、ガソリンスタンドの手前を左に曲がって、さらに3ヶ所ほどの曲がり角を標識の通りに進めば、やがて追分トンネルに着きます。
国土地理院の地図ではトンネルを通らずにまっすぐ山の方へ道が引いてありますが、現状ではまだこの道路が出来ておらず、地図は間違い。昭文社の山の地図が正確です。

長さ100mほどの追分トンネル。ここから先も長かった!
トンネルを抜けてひたすら歩きます。地図によれば追分から登山口までさらに1時間10分あまり。とにかく登山口に着かなければ始らないので、ひたすら歩き続けます。
途中、新たなトンネル工事をしている所、山中の三叉路、大きな変電所、川底が真っ平らな不気味?な川、舗装路の終点に停めてある数台のクルマ、その先の砂利道などなどをやり過ごし、おにぎりを1コ食べ、さらに数本の林道を横切った先、草の生い茂った箇所に唐突に登山口はありました。
ふぁ〜、遠かったぜ。この少し先にあった登山ポストに届けを投入し、やっと登山の開始です。
ところで「ふぁ〜」はFarに掛けてます。念のため!

変電所を過ぎた先にいきなり現れた、底が真っ平らに固められた不思議な川。写真では小川?に見えるけど実物は幅が20〜30m以上はあったのです。

登山口まで遠いなぁ…

ようやく登山口に着きました。ここを左に登っていくのです。
背の高い草薮を少し歩いた先からいきなり急登が始りました。今日は陽射しが暑く、こりゃきついなぁと黙々と登ってると隊長からちょっと待っての声、なんかフラフラする〜って…。持っていた飴を幾つかあげ、水を飲んだらようやく人心地ついた様子。
その後も急な狭い尾根をぐんぐん登っていくので高度感があり、こういう狭くて高いのが苦手な隊長は相変わらずフラフラするぅを連発しています。途中、ストックを貸してくれと言われ、ザックから取り出しセットして渡すも、やっぱり登りでは使いづらいからいらないって、ワガママな隊長…。
そして「同行者が先にバテた場合、自分は平気なことが多い法則」を思い出し、一人ほくそ笑む隊員。こら今日は貰ったな!って何を?
シメシメと思いながら先頭に立って尚も登っていきますが、さすがにこの急登の連続では平気なはずの隊員もへばって来だしました。1200〜1300mを過ぎたあたりでその歩みは亀のごとし。
それでも前回の高川山での反省から立ち止まること無く、ギアを超スローに切り替えてゆっくりゆっくり登るうちに、先にバテたはずの隊長は遙か高みを行っています。えっ、隊長ずるい!
見えなくなった隊長を確かめるため時々手をパンパン、パンパンパンッと叩くと、上の方から小さくパンパン、パンパンパンッて返事が聞こえてきます。21世紀になってもですね、原始的な通信方法使ってるんです、我が隊は!
ヒィーヒィーとアゴを出しつつもゆっくり登っていけば、やがて上の方に尾根っぽい所が見えてきました。おお!あの辺がきっと清八峠だなって思うと、やっぱり元気が回復してきます。
人間、目標が見えていれば苦しくても頑張れるんです!
調子にのってさらにパンパンっと手を打ち鳴らしながらせっせと登っていけば、やがて道がすぅーっと平らになり、ついに清八峠に到着!

峠の稜線に出ればいきなり風が涼しい!疲れた身体も一気に癒されます。
ここまで登ってくれば、この先は比較的楽な稜線歩きのはずなので気分的にも楽になり、隊員はあちこち写真を撮ってはしゃいでいます。隊長は早速おにぎりを食べています。
葉が落ちた枝から本社ヶ丸方向を透かしてみれば、岩場の上には人影が。ああ早くあそこまで行きたい!

風が気持ちよかった清八峠。隊長は到着して真っ先におにぎりを食べはじめました。

峠からすぐの岩場を登る隊長 のおしり 。
隊長がおにぎりを食べ終わるのを待って早速本社ヶ丸へと歩き出しました。ここまでの登山道と違って稜線上は岩が多くなり尾根も細いので、高い所まで登ってきたなぁって実感がひしひし。
最初の岩場を隊長が登ったのを見届けてから隊員も続きます。
そうしてやってきた岩のテラス、ここは文句無しに最高!でした。大岩が切り立った絶壁状なのでとにかく見晴らしがいいのです。東側以外のぐるりと330度くらいが見渡せます。そして空は真っ青!こんなに気持ちいい場所ってあるんだ!もう言うこと無しです。良くある表現ですが、本当に心底「これまでの疲れが吹っ飛んだ」のでした。

テラスから西北西の方向です。写真の真ん中、山塊のくびれた所が笹子峠だと思います。その右端の三角形は笹子雁ヶ腹摺山です。さらに奥の薄い稜線は棚横手かな? もっと北の方角には大菩薩嶺も見えました。

岩のテラスのすぐ下は絶壁。上に立ってみたけど、結構怖かったっす。

富士山を眺める隊員。超キマってます(と本人は思ってます)。その富士山はお昼も過ぎていたので逆光の中、霞むように聳えていました。なので写真にはキレイに撮れなかったんです。

靴紐を締め直す隊長。隊長は怖かったのか、結局テラスの上には立ちませんでした。
あまりにもこの岩のテラスが素晴らしかったので、本社ヶ丸に着く前にここで昼食にしようよって進言したのですが、隊長は直前の清八峠でおにぎりを食べていたため却下されます。
なので先を目指し歩を進めることに。まずはすぐ目の前の岩場を登って、その先に続く尾根線を進んでいきます。この本社ヶ丸までの稜線は、途中かなり尾根が細くなった所もあり、おもわず隊長は「(お尻が)きゅっと締まるぅ」ってきわどい発言も。

岩のテラスから本社ヶ丸へは、すぐ東にあるこの岩のピークを乗り越えていきます。
いくつかの岩場を乗り越えて、30分ほどで着いた本社ヶ丸山頂は、静かで小さなところでした。
急登を乗り越えて辿りついた清八峠での達成感や、続く岩のテラスでの圧倒的な開放感の後なのでどうしても感動が薄れがちでしたが、どうしてここも見晴らしは素晴らしく、実に気持ちのいい場所なのでした。
山頂には我が隊と、先行していた単独行の人がいるだけ。一息入れたあと、この静かな山頂でおにぎりを味わっていると、遠く下の方からコォーって風がやって来る音が聞こえます。今ここは無風なのに音が聞こえてしばらくすると近くの木がザワザワザワって鳴りだします。
おぉ!近づいてくる風の音って生まれて初めて聞いたわ!って隊長に報告する隊員。長く山登りをしてきた人には珍しくもないでしょうが、初心者隊員はこんなことでも感動するのでした。

本社ヶ丸山頂へついに到着。(山梨県の立てた標識)

山頂はそう広くはありません。三ツ峠が真南に見えます。
(手前は都留市、奥は大月市の立てた標識。この他にも三角点とあともう1本標柱が…)
のんびりとおにぎりを味わい、さてこの先をどうしようか?と地図を見ながら隊長の判断を仰ぎます。
隊長は、来る時に延々と歩いたあの舗装路をまた歩くのが嫌だってことで、帰りはこのまま稜線を東へ進み、鶴ヶ鳥屋山(つるがとやさん)手前のヤグラ跡分岐から笹子駅へ降りるルートに決定しました。
地図上のコースタイムを合計し日没で暗くなる前、4時半には下山(林道終点)出来るだろうと目星を付け早速行動開始です。でもこの時の計算に休憩などの余裕時分を入れるのを忘れていたんですよね。

本社ヶ丸からの下りは山頂の南側にある目立たない登山路を降りて行きます。
しばらくは岩の多い急な坂を慎重に降りていくと、やがて道は落ち葉を敷き詰めた丸っこい稜線の歩きに変わりました。時刻はまだ2時過ぎですが、既に傾きはじめた太陽を背中に受けての歩くこの辺りは、何だか子どもの頃を思い出さる場所です。初めて通る所なのになんだか懐かしい雰囲気。ここはちょっと忘れがたい稜線歩きになりました。(でも、ココはいいなぁって感じ入ってたから、この場所の写真を撮るのを忘れたのです!)

本社ヶ丸山頂から15分ほどで着いた分岐地点の看板。手書きがいい味を出してますね。

稜線上ではつねに鶴ヶ鳥屋山を正面に見ながら歩きます。
本社ヶ丸山頂までは何組かのパーティーと会いましたが、その先のこちら側は全く人の気配がありません。なので熊よけの鈴を持っていない我が隊は隊長が時々手をパンパンっと打ち鳴らして歩いてます。
そこで隊員は犬の遠吠えの真似をすればいいんじゃないの、とひらめき?一分おきくらいに「ワォーン、ワォワォワォッ!」って犬になりきって歩いてます。
後ろで隊長も真似しつつも恥ずかしいのか小さい声で「ワンワンッ」って。
何やってんだ、我が隊は。
鶴ヶ鳥屋山を正面に見つつ、ワンワンッとうるさい我が隊はずんずん歩いて行きます。そして角研山(つのとぎやま)を過ぎた小さな岩のピークで、本社ヶ丸山頂を出て以来の休憩としました。ポットから熱いお湯を注いで飲む酸味の利いた紅茶がおいしい!
大福をつまみながら、犬の気分から人間に戻ってリラックスタイムです。
と、ここで後ろから足音が。単独行の青年登山者が、休憩する我が隊の横を颯爽と追い越していきます。
ん?この間隔で後ろを歩いてきたってことは、あの犬の遠吠えを全部聞かれてたんか?
恥ずかしいったらありゃしない!

角研山から左へ降りる(笹子駅への)道は踏み跡もしっかり付いており、昭文社の地図にも実線で載っているんですが、現地には標識が出ていないんです…。ここを行こうかと迷ったんですが、結局はこのままヤグラ跡まで行ってしまいました。
休憩後、少し歩けば目指すヤグラ跡とその少し先に笹子駅への分岐点が登場。面白かったこの稜線歩きともお別れです。
この笹子駅からのルートを登ってきた人の話をネットで幾つか読むとかなりの急登らしい、と言うことは下山時にはかなりの急降下ってことになります。慎重に行こうと自分に言い聞かせ、いざ一歩を。

やっと着いた笹子駅への分岐。道は枯れ葉に覆われています。
ところで本社ヶ丸山頂を出発する際、ここからは下山行程だからと靴紐の足首側をきつく締め直したのですが、これが締めすぎたせいなのか右の向こう脛の下がかなり痛い。
痛ければ紐を少し緩めりゃ良いのに、その時は紐のせいとは思わず筋肉痛だと思っていたのですね。下山するうちにどんどん痛くなってそれでも我慢して歩いてたんですが、このため肝心な時に力が入れられなくなってしまい、あとでえらい失態をする羽目に。

ヤグラ跡あたりで、木の間から透かし見た滝子山。そろそろ夕方って頃。下山時刻がこんなに遅くなっては駄目です!
この登山路にはプラスチック製の階段が延々と埋め込んであるのですが、これと浮いた岩が多量の落ち葉に隠れて見えづらく、とんでもない所を踏んだりして二人ともかなり難儀します。
途中、山腹を横切る工事用林道と交差してから登山路はいっそう草深くなって行きます。鉄塔の建つぽっかりと開けた場所を過ぎ、そして脚の痛みがピークに達しようかという頃、沢の音が聞こえはじめ、そして樹々の間からは白いものが!
ああ、道路?建物?クルマ?って思うと、とたんにホッ。
でも沢の水が白く反射していただけなのでした。
それでもこの沢(船橋沢)に降りてきさえすれば、この先には林道(舗装路)があるはずなので随分気が楽になりました。踏み跡は何カ所かで沢を渡って対岸に続いています。
二度目の渡渉(沢渡り)で隊員は流れの中の小さな岩に脚を載せ、これが動かないことを確認してぐっと踏み出した瞬間、つるんと滑ってジャボーン!
こりゃいけないとグッと踏ん張ろうと出した右脚が、痛くてへろへろになった方だったので、これまた全然支えきれずにそのまま身体ごと 入水 ダイブしてしまったのでした。
普段ならすっと立ち上がれるのだろうけれど、なぜか背中のザックが重く脚にも力が入らないので、水中でアウアウもがく隊員。見かねた隊長が頭を持ち上げてくれ、ストックを渡してくれたので、やっとなんとか立ち上がり脱出できたのでした。
隊長はかなり心配して、怪我は無い?大丈夫?と尋ねてきますが、平然を装いたい隊員、さっさと先に歩き出します。
でもここは一息ついて冷静にならなければいけなかった。やっぱり動揺していたのでしょう、その先の関係ないところで再び渡渉して対岸に渡ってしまったのですが、これが道間違いでした。
そのまましばらく歩けば踏み跡も無くなり、対岸を見ればちゃんと水道用のパイプが通ってるじゃないか、何をトチ狂ったんだろうってことで再び渡った地点へ戻ってコースに復帰です。予定より遅くなった沢到着のため、この時点で日は山の陰に完全に入り、沢一帯はかなり薄暗くなってたんでそれもあったのかなと。本社ヶ丸山頂で時間読みのとき、休憩時間を入れ忘れたのがこんなところで響いてくるんですね。
半濡れのまま薄暗い中を歩き堰堤を2ヶ所越えた先に、水道設備の建物と舗装路にたどり着きました。やっとここで緊張を思いっきり解きます。ホッー!
この先、笹子駅までの林道歩きは暗い道となりヘッドライトを付けての歩行ですが、駅近くなって空を見上げれば満月に少し欠けた明るい月が。真っ暗にならず薄ぼんやりと見えていたのはお月様のお蔭だったのですね。
笹子駅まで戻ってくればちょうど良い時間に電車があります。登山用のウェアは林道を歩くうちにほとんど乾いていました。
大月で後続の特急かいじ号に乗り換えればそこはすっかり文明の中。ついさっきまでの下山の緊張感が遠いことのよう。
でもですね、今回も物凄く充実した山行だったって記憶はいつまでも残るのです。
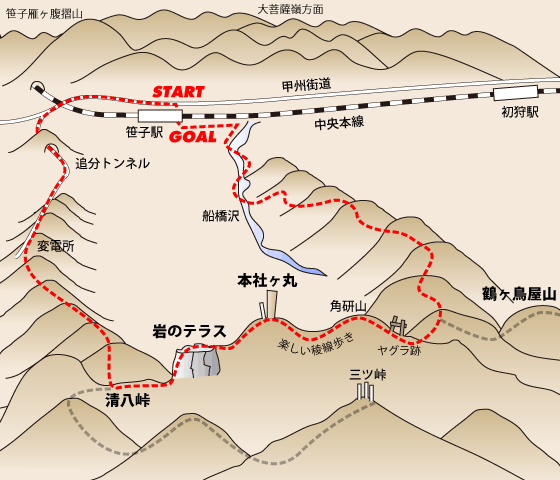
(2009.11.4 隊員n記す)
 前回の
前回の